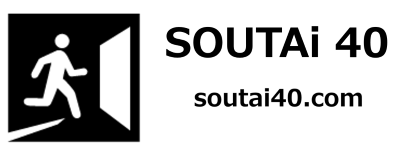サラリーマン時代によく読んでいた本に『峠の群像』(堺屋太一著 文春文庫 1987)がある。
江戸時代の「赤穂事件」をテーマにした小説で、NHK大河ドラマ(昭和57(1982)年)にもなった。
今も頭に残っている印象的なシーンがある。
元禄14(1701)年3月14日、赤穂藩主の浅野内匠頭が吉良上野介を江戸城松の廊下で斬りつけた。
結果、赤穂藩は改易(取り潰し)となり、浅野内匠頭は即日切腹となった。
藩が消滅するので、藩士は全員解雇となる。
退職金はいらない
藩の消滅は企業の倒産に似ている。
赤穂藩が解散する前に、現代企業の「退職金」のように、藩に残ったお金を藩士に分配することになった。
が、分配金の分け方について、筆頭家老の大石内蔵助と財政担当家老の大野九郎兵衛との間でもめた。
大石内蔵助は「身分の低い藩士ほど手厚く分けてやりたい」と主張する。
大野九郎兵衛は「高禄の者は家族や召使いなど養う者が多いから、身分の高い者ほど多く配るのが当然」と思っている。
結局、大石内蔵助の案が通り、大石は大野に次のように付け加える。
「ついでながら、某(それがし)は一切受け取りませぬでな、その分九十両は中小姓組にでも上乗せするように考えて下されや」
つまり、「大石が受け取るはずの分配金を全額身分の低い者に渡してくれ」というのだ。
大野九郎兵衛は「やられた!」と思った。
働きの成果よりも自己犠牲の多寡によって人を評価したがるのは、日本人、とりわけ低成長社会のそれの不幸な特性である。大石内蔵助の分配金受領権利の放棄は、成長性のない「お米の経済」にあえいでいた元禄時代の武士たちに、最も分かり易い自己犠牲を見せつけるものだろう。
『峠の群像(四)』p.65
“成長性のない「お米の経済」“というのは、武士の収入が年貢(お米)に依存していたことを指す。
元禄時代は好景気で物価が上がっていったが、米の価格はそれほど上がらなかった。
結果、収入が米の武士の実質収入は下がっていって困窮化していた。
収益が上がらない低成長の世界にいる者は、どれだけ成果をあげたかよりも、どれだけ自己犠牲を払ったかで評価される。
自己犠牲は文化
「自己犠牲」というのは「長時間残業」「徹夜」「武勇伝」「苦行」「空気を読んで我慢する」と置き換えてもいい。
つまり、よりよい未来考えることを放棄した「逃げ」だ。
「なぜ、定時のチャイムが鳴っても誰も帰らないのか」
「なぜ、無駄に徹夜したことを自慢気に語るのか」
サラリーマン時代に本書を読んで、原因がわかった。
江戸時代から数百年かけて自己犠牲が文化になってしまっているのだ。
大石内蔵助が「われらの自己犠牲を一時的な流行ではなく、文化にしたい」と言ったかどうかはわからないが。
文藝春秋 (1986-12)
売り上げランキング: 572,285