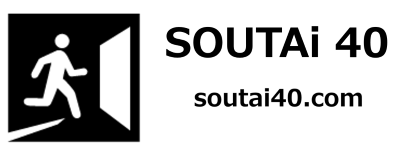松本清張の小説「いきものの殻」を読みなおした。
『延命の負債』 (角川文庫 1987) に収められている短編小説で、初めて読んだのはサラリーマン生活を始めて数年たった頃だった。
会社とは、社員の生き血をすすって生きながらえる怪物?
あらすじ
主人公は東京の商社に30年勤務して総務部長のポストを最後に退職した男だ。
彼は毎年会社のOB会に出席していた。
本当はあまり出席したくなかったのだが、OB会の出席資格が「次長以上の元社員」というのに「卑屈なプライド」をくすぐられて毎年出席している。
話の内容は小説を読んでもらうとして、彼はOB会の帰りに東京駅の方に向かって歩いていた。
ふと見上げると、かつて30年間勤めていた会社のビルの前に来ていた。
彼は会社の建物が「生き物」に見えた。
どんな生き物に見えたか。
作者・松本清張の表現が傑作なので引用する。
建物が、いつまでも生きている生物にみえたのである。この内部で働いている人間は年々に老いて辞め、死んでゆく。しかし、この建物だけは、会社創立よりすでに六十年になるが、生存機能を停止することを知らない。これからも何十年か、何百十年かを生きるかもしれない。その間に、何千人という人間が、この内部で栄養を吸い取られ、吐き出されて斃死(へいし)することであろう。人間は死んでゆくが、この建物ばかりは、栄養にふくらみ、動脈に赤い血を殖やしてゆくように思われた。
p. 145
会社という「生き物」
この文を読んだときはまだ駆け出しのサラリーマンだった。
「会社」ってなんて恐ろしいところなんだ、と思った。
何千人もの社員の「栄養」を吸い取りながら生きながらえる「会社」という生き物……。
ところで、なぜ主人公の男は会社をこのような「生き物」だと思ったのだろうかと考えてみた。
彼は会社に「生きるエネルギー」をすべて吸い取られ「人間の抜け殻」になってしまっているのではないだろうか。
30年という時間をすべて会社に捧げた「人間の抜け殻」。
小説のタイトル「いきものの殻」に込められたメッセージを読み解きながら、自分の会社人生に重ねあわせて読むのがおすすめだ。
※収められている小説
延命の負債
湖畔の人
ひとり旅
九十九里浜
賞
春の血
いきものの殻
津ノ国屋
子連れ
余生の幅
三味線
月